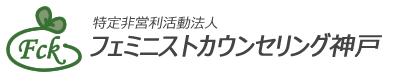春の富山で、日本フェミニストカウンセリング学会の全国大会が開かれました。
コロナ禍を経て、会場に参加者が集い、語り、聴き、食し…
とてもにぎやかで、エネルギッシュで、なんだか懐かしい感じもしました。
私は割と人見知りなのですが、フェミカン学会の集まりでは、
はじめてお会いする方とも、地域や年代を超えて、素直に、正直に話ができてしまいます(^^)
女性支援について。それぞれの活動。自分のこと、、話と興味は尽きません。
また、博多ウィメンズカウンセリングのスタッフの方と一緒にワークショップも担当しました。
”女性”として生活するなかで、私たちがどのような神経系のパターンを作り出し、適応してきたのか
を、参加者のかたとともに探求しました。
ジェンダーの視点を共通項として、ポリヴェーガル理論を使った理解やアプローチについて学びを得ました。