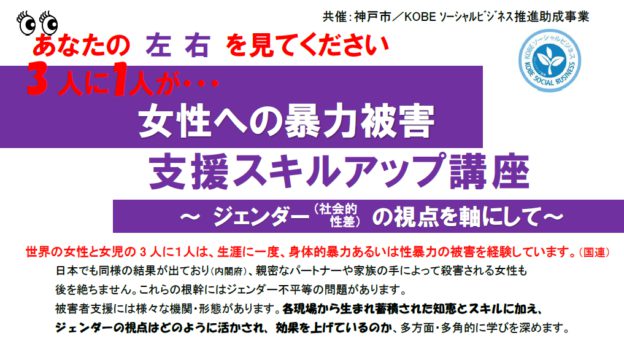2018年1月13日(土) 10:00~16:00
@神戸市男女共同参画センター
「解離」
暴力被害や性暴力被害による症状の一つとして
ときどき耳にする方もおられるのではないでしょうか?
でも、一体
どのような症状で、
解離の症状を持った当事者は日常生活でどのようなことに困り、
私たちに求められる理解ある対応とはどのようなものなのでしょうか?
解離(だけではありませんが…)の症状を持ちながらも、
日常生活を安全に送ることで
被害者は回復されます。
安心して回復ができるあたりまえの社会になればいいな、と思います。
そのために、
自分の症状や困難を理解してもらいにくい当事者
相手の状態を理解した対応に苦慮している支援者や周囲の人
ちょっとしたズレが二次被害やさらなる傷つきにならないよう
基本的な症状や対応を学ぶ機会になることと思います
今回の養成研修は、性暴力やDV被害者支援、また支援者の養成をされている
東京のNPO法人レジリエンスが主催される研修です。
フェミカン神戸も、今回の開催にあたり、共催をさせていただいています。
是非ご参加ください
お問合せ・お申込みはNPO法人レジリエンス(kairi.kansai@resilience.jp) まで。
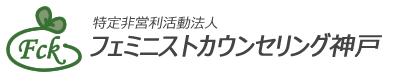











 と思います。
と思います。










 本人がどう生きたいのかを感じ、言葉にし、
本人がどう生きたいのかを感じ、言葉にし、 を感じた時間でした。
を感じた時間でした。
 つながった手を離さないこと
つながった手を離さないこと