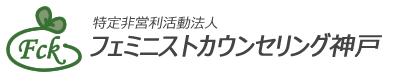2月20日、兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会 研究会で、
「配偶者暴力等の理解と福祉における支援に期待するもの」というタイトルでお話しをしました。
研究会ご参加の方々は、兵庫県県民局や市町の福祉事務所、児童相談所など福祉関係事務所の管理職のみなさまです。
DVのサバイバーの方と関わられる部署ですので、DVに関する知識を持ち、理解を深めていただけたらと考え、お話しさせていただきました。
DV被害を受けた人は、その影響から気持ちが安定せず傷つきやすくなっています。
そんなとき、DVの特性や被害者の置かれた立場を理解しない支援者に接すると、
その言動によって更に傷つけられてしまうことがあります。
それを「二次被害」と言います。
二次被害を与えないためには、DVについての正しい理解が必要です。
支援者に理解されていると思うと、相談者は安心して話すことができますね。
講演ではDVのしくみ、被害者の心理、DVによる影響だけでなく、
DVを目撃した子どもの被害やその影響についてもお話ししました。
そして、避難の前後だけでなく、中長期的な支援が必要だということもお伝えしました。
1時間でお伝えするには盛りだくさんの内容でしたが、みなさん、とても興味を持って聞いてくださいました。
DV支援は、被害者が精神的にも経済的にも自立できることが目標です。
講演でのお話が、参加した方々の現場での指導や支援に役立つことを願っています。